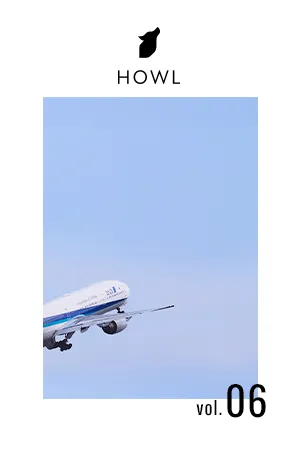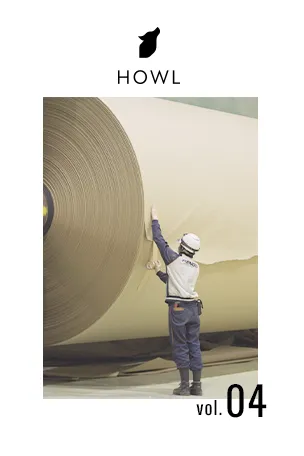全日本空輸株式会社
デジタル変革室イノベーション推進部
データドリブンチーム マネージャー
(本プロジェクト推進時)ANA X株式会社
デジタルマーケティング部 チャネル企画チーム
紺野 元気 氏
「マイルで生活できる世界」を目指して。航空事業と非航空事業をつなげる “スーパーアプリ” への挑戦。
Story of IDEA
2020年以降、業界がコロナ禍の打撃に襲われる中、航空業界最大手のANAもまた、ビジネスモデルの変革が課題となっていました。 そして2021年春、既存アプリを大幅にリニューアルするスーパーアプリ構想を発表。 グループ全体のサービス認知を高め、顧客のライフタイムバリューを高めるためのプロジェクトをスタートさせました。 航空事業と非航空事業をつなげるコア要素がマイルであると位置付け、「マイルで生活できる世界」を実現するためのアプリを目指した本プロジェクト。フェンリルは、アプリの企画から開発・リリース、またグロースまで、サービスデザインのパートナーとして対応しました。 さまざまなサービスとの接点、その受け皿となるスーパーアプリ(ゲートアプリ)として生まれ変わらせるプロジェクトの、リリースまでの道のりを振り返っていただきました。

THEME 01
開発の経緯/背景
ユーザー体験の向上を目指して、 多岐にわたるサービスを紐解く。
───「マイルで生活できる世界」を起点にしたスーパーアプリ構想が発表された当時、どのように受け止めていましたか?
2020年の秋ごろですが、その頃は外部に出向していた時期でしたので、ニュースで内容を知りました。スーパーアプリについても具体的な話はまだなかったので、どういった取り組みなのかイメージできなかったのが率直な感想でした。
───どのような経緯でプロジェクトメンバーとしてアサインされたのでしょうか
ちょうどその頃、今後のキャリアについて考えていたところで人事担当からこの案件の紹介を受けて、スーパーアプリ構想のプロジェクトメンバーとして参画することを志望しました。
詳細がまだ分からない状態ではありましたが、2016年にANAアプリのリニューアルを担当した際、新しい開発手法を取り入れたプロジェクト推進をしていたので、そのときの経験を生かせるかも、という考えはありました。

───プロジェクトに参加されて、まずどんなことに取り組みましたか?
会社にとって大きな挑戦ということもあってか、当初はトップマネジメント層が中心となって構想検討を進めている、ややイレギュラーなプロジェクトでした。
私自身はLINEやメールなどのプロモーション配信やチャネルごとの顧客体験のマネジメントなどのミッションがあったのですが、並行してRFP※の準備もすぐに進めていく必要があったので、アサイン直後から忙しく対応していた記憶があります。
※RFP
プロジェクトを発注する際に、外部のベンダー(開発会社やパートナー企業)に課題や目標を伝え、具体的な技術仕様やサービス内容の提案、見積もりなどを依頼するための文書
───RFPはゼロベースから作成されたのでしょうか
素案のようなものは8割ほど出来上がっていました。ただ、ANA経済圏の具体的な定義がなされているというよりは、「取り組みの全体資料」という印象でした。
そんな中でも2022年度にスーパーアプリを出すことは決まっているという状況だったので、社内からは「スーパーアプリって何をするの?」という声をたくさん聞きました。「先の見えない高い山を前に、自ら山頂も登り方も定義していかなければならないんだな……」という気持ちだったことを覚えています。

───「スーパーアプリ」に向き合うにあたって、チームメンバーとはどのような議論をしましたか?
はじめは「ANAグループのサービスを掲載するメディアのようなアプリ」という認識で、まずは他社アプリの調査から始めました。ただ参考にするということではなく、「ANAだからこその価値」を模索する日々だったように思います。
単なるサービスの寄せ集めにならないようにしたいというのがあって、惹きつけられるコアな価値を起点に、その周りのサービスをどう見せるのかを議論していきました。
───議論を進めるにあたって最も難しかったことは何でしょうか
日常シーンも対象としたアプリであるため、「必ずしも航空機の利用を前提としない」という視点は苦慮しました。航空機ユーザーではない方にどのような価値をお届けするかという、これまでのビジネスモデルでは通用しない点がすごく難しかったです。
どのようなコンテンツにするべきか、ニュース発信や占い、会員同士の情報交換コミュニティなど、アイデアの発散をしていきましたが「これだ」というものがなくて。しばらく発散のフェーズが続く中で、航空事業の1本柱からの脱却は簡単なことではないと痛感しました。

───チャネルだけではなく事業レベルのことも考えられていたように感じました
たしかに当時は、経済圏事業のビジネスも同時並行的に立ち上げを検討していた時期でしたので、私を含め他のメンバーも、論点が「ビジネスの立ち上げに関する話なのか」あるいは「ビジネス表現の場であるチャネルをどう考えるのか」というのを混同していたところがありましたね。論点の切り分けが難しかったです。
───各事業部とはどのようなやりとり、調整をされていましたか?
新しいチャネルが誕生すると、各部門から「サービスや商品を掲載してほしい」という依頼が来ます。コンテンツの充実は大切ですが、要望をすべて受け入れて反映するというのは、今回目指すスーパーアプリにはミスマッチだと感じていました。アプリとしての統一感や使い心地も悪くなってしまいますし、「何のためのアプリなのか」がお客さまにとって分かりにくくなると考えていたためです。
事業の成長を支えたい思いはもちろんありましたが、「ユーザーはそれを求めているのか?」という視点とバランスを取りながら、各事業部と調整を重ねていきました。

───どのように落とし所を見つけたのでしょうか
議論を重ねるうちに、アプリはあくまで「お客さまとのコミュニケーションの起点」であり、我々が目指すことは「デジタルタッチポイントを集約するゲートアプリ」であるというところに行き着きました。我々が作るゲートウェイに顧客を呼び込み、そこを通して各事業部のサービスへシームレスに連携する、という構図です。
当時は「新生ANA X」として事業をスタートし始めたころで、各部門が自分たちのチームがどのようにゲートアプリに関わっていくのかを模索していました。一定の混乱は予測していましたが、今振り返ってみると、事業/価値/機能という切り分けをよりうまく行える余地があったと考えています。
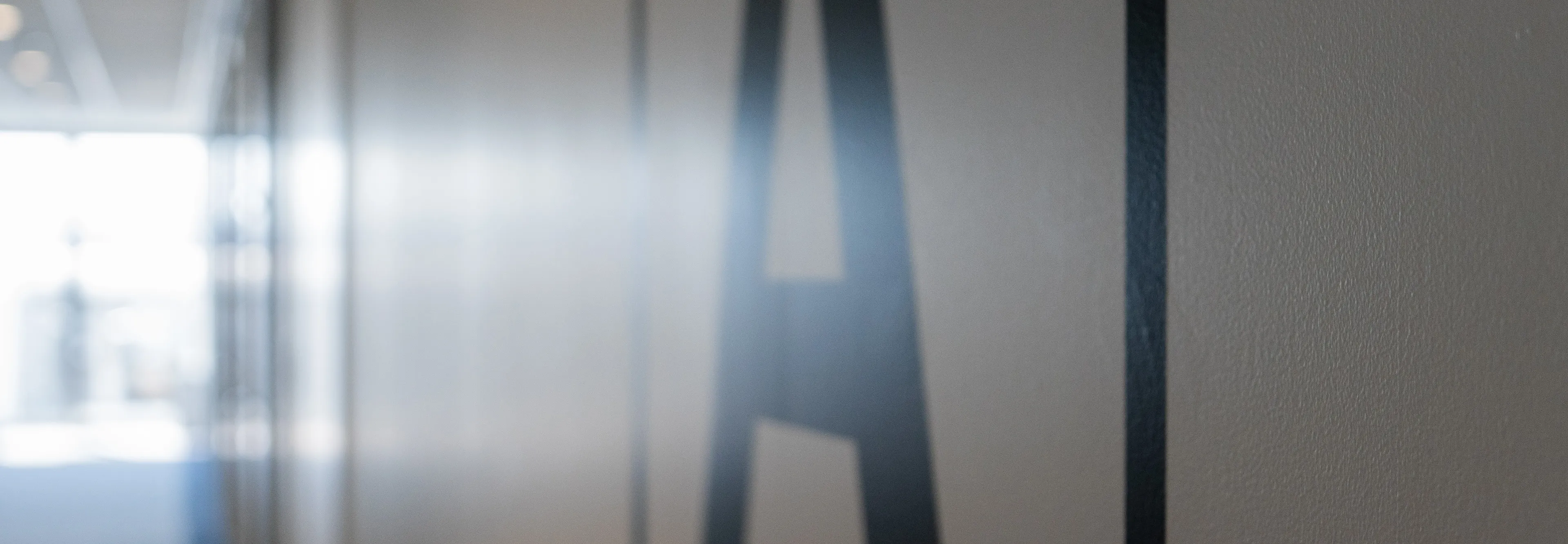
THEME 02
完成までの道のり
ANAらしさと新しい価値、 事業にコミットするコンセプトの創出。
───ベンダー選定時に重視されていたこと、フェンリルを選ばれた理由についてお聞かせいただけますか
アプリのUXや機能だけではなく、お届けしたい価値の議論を一緒に深めることができるかどうかを一番に考えていました。フェンリルさんは、見た目の使いやすさだけではなく、「お客さますら気付いていないニーズを見いだしてアプローチする」という提案が魅力的でした。
正直に言うと、価値提案の面ではフェンリルさんより他のベンダーの方が派手というか、ワクワクする部分がありました。ですが、企画に割ける期間が約4か月という限られた中で、着実に一定の結果が出るまで推進してもらえるかというのも重要でした。
今の自分たちに合った進め方ができるという点で、実直な姿勢で向き合ってくれたフェンリルさんが適任だと感じました。

───本格的なプロジェクトスタートして、この頃に感じていた課題などがあればお聞かせください
フェンリルさんとの関係性という以前に、社内メンバーが一枚岩になりきれていませんでした。まだ組織されて間がなく、さまざまなレイヤーのメンバーが集まっているということもあって、対等で自由な議論をしにくい空気感があったのかもしれません。
課題は存分に感じていたのですが、私自身がいちPMとしてどうするべきなのか見えていなかったというのが正直なところです。議論が停滞している中で、月1回の経営会議では一定の進捗を見せなければならないという、苦しい期間でしたね。

───そこからチームが同じ方向を向くようになった転機があったのでしょうか
「マイルが中心」という前提で価値の議論を進めていましたが、このアプリがコロナ禍の状況を好転させてくれるのではないかという期待の中で、それ以外の新しい価値を見いだす必要性を感じ始めていたんです。
そのために、お客さまの日常にある価値をいくつか仮定して、それをもとにユーザー調査を実施しました。その結果から「移動」「健康」「資産形成」「社会とのつながり」という4つの価値に絞ったことで、取り組んでいくことがはっきりしてきたように思います。
───ユーザー調査の結果をどう反映していきましたか?
4つの価値をすべて組み合わせる方法を模索しましたが、それぞれが独立しているので、UIの面でも落とし込みが難しくて。1つに絞ることになったのですが、スコープの調整にも悩みました。
フェンリルさんも含めて議論を交わして「移動」という価値に絞りましたが、個人的にはまだこのときは不安が強かったです。「これで行ける!」という自信は持てなかったのですが、プロジェクトを次のフェーズに進めることができたことにほっとしたのを覚えています。

───新しい価値を前向きに捉えられるようなったきっかけはあったのでしょうか
「移動」という価値に集中してみると、経済圏事業のふるさと納税やトラベラーズホテル、モールなどに関連づけることができると分かりました。移動のきっかけとしてアプリを開くところから、経済圏のプロダクトに触れてもらうという、自然な流れができていたんです。
さらに議論の中で「移動」という価値を「行動」という解釈に広げたのですが、そうすることで、絞る前に出ていた「健康」「資産形成」「社会とのつながり」という他の価値の部分も含む可能性も見えてきました。
単なるお出かけ情報のアプリではなく、ANAの事業にコミットできるポテンシャルを感じ始めたことで、プロジェクトが加速したことを覚えています。
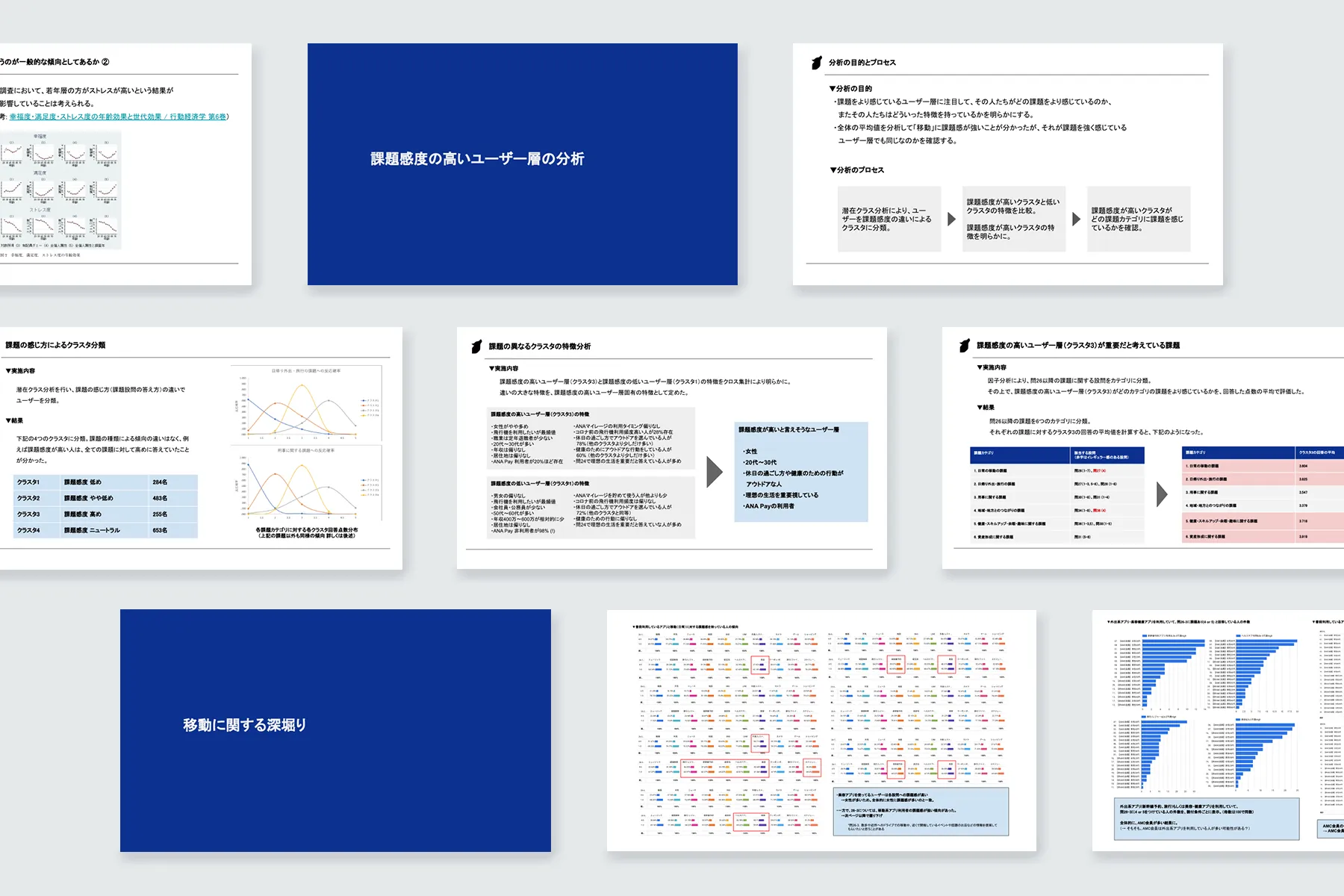
───構想フェーズを経て、現実的なところに向き合う要件定義で感じていたことをお聞かせください
限られた期間の中ですべての機能を一気にリリースすることが難しいことは分かっていましたが、「ある程度は実現できるのでは?」という感覚もまだありました。
ですが、企画内容を実現する新しい機能の要件を固める中で、次のフェーズへ先送りする機能が出てくることはやむを得ないと感じました。企画構想を進めてきたメンバーにとっては酷だと感じることもありましたが、先に進むためには確実なところを絞り切ることが重要でした。
フェンリルさんからはプロジェクト開始早々に、現実的なスコープや成功のための前提条件をいただきました。そのおかげで、過度に壮大な機能の検討に時間を費やすのではなく、身の丈に合った議論を支援していただけたことがありがたかったです。さまざまな場面で、意思決定の助けとなっていただき、スケジュール的にギリギリの中で、こちらの要望を飲んでいただいたところも多く感謝しています。
───開発フェーズで印象に残っている出来事を教えてください
ANAならではの付加価値という点で、特別感の醸成が課題でした。スーパーアプリにとって何が最適なUXなのか判断が難しかったので、フェンリルさんから航空のノウハウ以外の部分をサポートいただけたのは本当にありがたかったです。
───全体的なUIデザインについて、どういうことを意識されていましたか?
極力シンプルな画面構成にすること、ANAならではの特別感やプレミアムステイタスをどう演出するかという部分ですね。ANAのさまざまなブランド、コンテンツを掲載するメディアとして、お互いを邪魔しないことを意識しつつ、ステータス会員の方が、特別感を持てるようなデザインとの共存を目指していたので。
アクセシビリティに配慮したUIに刷新する必要もあったので、折り合いをつける大変さもありました。例えば、これまで採用していたアニメーションの表現ができず、情緒的な見せ方が難しかったこととか。ですが、そうした条件の中でもフェンリルさんにANAの青のイメージを美しく構成していただけた点に、非常に満足しています。
───開発テストフェーズでのフェンリルとのやりとりで印象に残っていることはありますか?
この頃になるとメンバーが増えてきて多少の余裕が出てきたのですが、テストケースをたくさん出すという環境の調整が物理的に大変でした。
ですが、フェンリルさんからは「用意してほしい環境」「レビューしてほしい観点」を明確にもらえたので、「何を求めているのか分からない」というようなことはなかったです。テストで品質を担保すべき事項についても議論を深め共通認識を持てたことは有意義でした。こちらがその要望に応える労力はかかりましたが、いつまでにこれが欲しい、というオーダーが分かりやすく、常に真摯に向き合っていただいた印象です。

THEME 03
リリース後の効果
データ活用を模索して、 グループ全体にシナジーを生むアプリへ。
───リリースを迎えて、プロジェクトを率いる立場としてどんなことを感じていらっしゃいましたか?
まずはリリースできたことにほっとしましたが、もしあと1か月伸ばすことができたら、何かまた別のアプローチがあったかな?と考えることはあります。
今日お話ししたこと以外でも、アプリマーケティングやプロモーション、ANAのプッシュ通知やメールマガジン、デジタル広告、キャンペーンなど、考えることが本当にたくさんあって。諦めなければならない部分もありましたが、当時置かれていた環境やスケジュール、少ないメンバーで成果を出せたことは、よくやれたと感じています。
───社内外の反応はいかがでしたか?
こうしたプロジェクトは遅延していくことが多いのですが、約1か月ほどのラグに収められたことも含めて社内の評価は高かったです。それが故に期待が高まったという側面もあって、「これはいつできるのか?」という声や追加要件のリクエストがどんどん上がっていきました。
プレッシャーはありましたが、こうした期待の声を受けて「無事に走り始めることができた」と実感できました。
一方でお客さまからは「特別感が失われた」という声も上がりましたが、貴重なお声として前向きに受け止めています。まずは枠組みをつくることができたので、今後改善していきたいと考えております。

───リニューアルでは、ANAならではの付加価値を提供する「スポット機能※」が追加されました。リリースにあたって意識されていたことはありますか?
※アプリの地図上でANAグループ社員がおすすめする店やマイルが貯まるスポットを検索できる機能。
ANAらしさを表現するにあたって、ANAグループの「人」のチカラをこのアプリにも反映させたいと思っていました。大切な機能だと考えていたので、社員への協力依頼にも力を入れました。例えば、社長に直接「ぜひ書いてください!」とお願いをして、書いてもらったものを社内ポータルに掲載することで、社内認知を高めていくとか。結果的に1stリリース時点で6000件近くのスポットが集まったのですが、客室乗務員をはじめ、みんな楽しみながら情報を寄せてくれました。
個人的にも、出身地方の定食屋の情報などを提供しています。勝手ではありますが、地域の大使になれたような気がしていて。航空業界に身を置くものとして、地域発展や観光業界を盛り上げ、お客さまの旅のプランニングの一助になれているのならうれしいです。

───今回はアクセシビリティ対応にも注力されていましたが、振り返っての所感をお聞かせいただけますか
当初はアクセシビリティに関する知識が深くなかったこともあって、フェンリルさんにお任せするというスタンスでした。ですがフェンリルさんから、スーパーアプリの拡張性と使いやすさはトレードオフの関係であるという懸念を強く言ってくださったことで、当事者意識を持つことができました。プロジェクトの柱のひとつとして一緒に考えられたことは、ANAにとっても大変有意義だったと思います。
その結果、社内のサービス基盤チームをはじめ、アクセシビリティの調査をお願いした外部企業からも一定の評価をいただけました。見た目のところだけではなく、一つのタッチポイントとしてアクセシビリティに誠実に対応していく姿勢、限られた期間でガイドライン上の主要な事項を実装した点を評価されたのだと感じています。

───今後の「ANAマイレージクラブアプリ」に期待することは何でしょうか?
私たちが向き合った「日常に接点」という、ANAとしてはこれまでにないチャレンジを今後どう生かしていくかというのが課題だと思っています。
データを用いて、アプリそのもののグロースだけではなくANAグループとして顧客理解を深めるなど、新しいビジネス価値創出の在り方をアプリに求めていきたいです。
私は、リリース後にプロジェクトから離れたので、ユーザーがこの機能をどのように捉えているのかというのを見届けられませんでしたが、持続的に開発、運営する体制を整えてお客さまの手元で寄り添うアプリとして発展させてほしいです。このマイレージクラブアプリが、ANA全体のシナジーを生む存在になることを楽しみにしています。